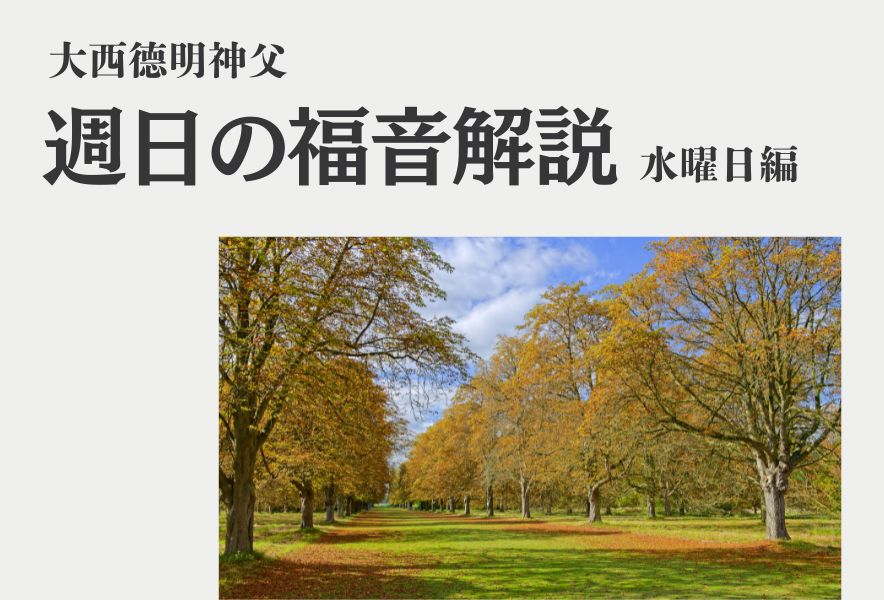ルカによる福音書9章1–6節
1 さて、イエスは十二人を呼び集め、すべての悪霊を制し、病気を癒やす力と権威を、彼らにお与えになった 。 2 そして、神の国を宣べ伝え、病人を癒やすために、彼らを遣わすにあたって、 3 仰せになった、「旅には、何も携えてはならない。杖や袋も、パンや金も、また下着も二枚持ってはならない 。 4 どこかの家に入ったなら、そこに留まり、そこからまた旅を続けなさい 。 5 もし、誰もあなた方を受け入れてくれないなら、その町を出ていく時に、彼らに対する証しとして、足の塵を払い落としなさい」 。 6 そこで、弟子たちは出かけて行き、村から村へと巡り歩き、至る所で福音を宣べ伝え、病気を癒やした 。
分析
イエスが十二使徒を派遣する場面です。ここでの中心的なテーマは、「神の国の到来を告げる使命と、それを担う者に必要な信頼の姿勢」です。短い記述の中に、宣教者に求められる霊的姿勢、実際の振る舞い、そして神との関係性が深く刻まれています。
まず、イエスは「すべての悪霊を制し、病気を癒やす力と権威」を弟子たちに与えられます(9:1)。ここで注目すべきは、「力」と「権威」の両方が与えられている点です。これは単なる癒しの能力やカリスマ的影響力ではなく、神の支配(バシレイア)の現実化を担うための霊的信託を意味します。弟子たちは、ただ模倣的にイエスの働きをするのではなく、神の国の代理人として、その現れを行動で示す者とされたのです。
次にイエスが語る派遣命令(9:3–5)は、きわめて挑戦的な内容です。「何も携えるな」とは、物質的自立を一切否定するのではなく、派遣される者が神の摂理と人々のもてなしに全面的に信頼して生きるべきであるという宣言です。杖や袋、パン、金、着替えすら不要とされたのは、宣教が力や準備によって成立するのではなく、信頼と従順によって成立するという霊的原理を際立たせるためです。
さらに、「どこかの家に入ったなら、そこに留まれ」とあるように、弟子たちの生活拠点は宿を転々としないことで、利得や人気を追わない一貫した姿勢を示すことが求められています。また、「受け入れられなければ、足の塵を払い落とせ」という命令は、拒絶を恐れず、しがみつかず、ただ忠実に神の言葉を告げる者であれという、福音宣教の自由と潔さを示しています。
この一連の記述は、弟子たちの派遣が単なる伝道活動ではなく、神の国そのものの到来を現実にする出来事であることを如実に表しています。彼らが告げ、癒すすべての行為は、神の支配がこの地に実際に触れているという証です。
神学的ポイント
この派遣の物語には、以下のような神学的ポイントが濃縮されています。
1.派遣とは、神の権威に生きること
イエスは自らの「力と権威」を弟子に分与します。それは個人の能力ではなく、神の支配を代表する代理人として生きるという霊的アイデンティティです。現代においても、教会が宣教に携わるとき、私たちは自らの計画や資源によってではなく、委ねられた神の権威に基づいて行動するべきです。
2.「持たずに行く」ことの信仰性
何も持たずに行くという命令は、宣教の本質が依存ではなく、信頼にあることを強調します。神が備える、神が守る、神が語る——その信仰を体現することが、福音の真実性をもっとも雄弁に語るのです。弟子たちは「必要なものを持って出る」のではなく、「神に必要を満たしてもらう」ために出て行くのです。
3.拒絶される自由と、語り続ける責任
「足の塵を払う」という行為は、呪いではなく、神の言葉を聞く責任がその町にあることを明確にする象徴的行為です。受け入れるか拒むかは聞く側の責任であり、語る者は忠実に語り、執着せずに次へと進む。これは、結果ではなく忠実さにこそ神の評価があるという福音の原理を表します。
4.宣教とは神の国の現在化
弟子たちは「神の国を宣べ伝え、病人を癒やした」(9:2, 6)。つまり、言葉と行為が分離されていません。語ることと癒すことの一致こそが神の国の現れであり、それは単なる「教え」でも「奇跡」でもなく、神の愛と義の具現化です。
講話
この派遣の物語は、今日の私たちにも問いかけてきます。「あなたは、何を持って出ていこうとしているのか?」という問いです。
私たちは往々にして、準備が整ってから、訓練が終わってから、確信が持ててから動こうとします。しかしイエスは、「持たずに行け」と言います。それは神の国の働きが、人間の十分さではなく、神の十分さに根差しているからです。
また、「受け入れられなかったら、塵を払って進め」という言葉は、失望に囚われない信仰を私たちに教えます。誰かに断られた、誤解された、無視された——それでも、福音は進みます。失敗を恐れず、ただ忠実に語り、神の働きに道を譲る。宣教とは、成功ではなく信頼によって成り立つ旅なのです。
弟子たちは、名もない村々を歩き、ひとりひとりに手を差し伸べ、神の国を告げました。それは派手な活動ではありませんが、世界を変える始まりでした。今日、私たちもまた、名前の知られない誰かのもとへ、癒しと福音を携えて向かうことができます。
それは特別な訓練や肩書ではなく、「持たないことを恐れない心」「受け入れられなくても語り続ける信頼」から始まります。
「わたしは、そのためにあなたを遣わした」。
この言葉が、今日、私たち一人ひとりに語られています。