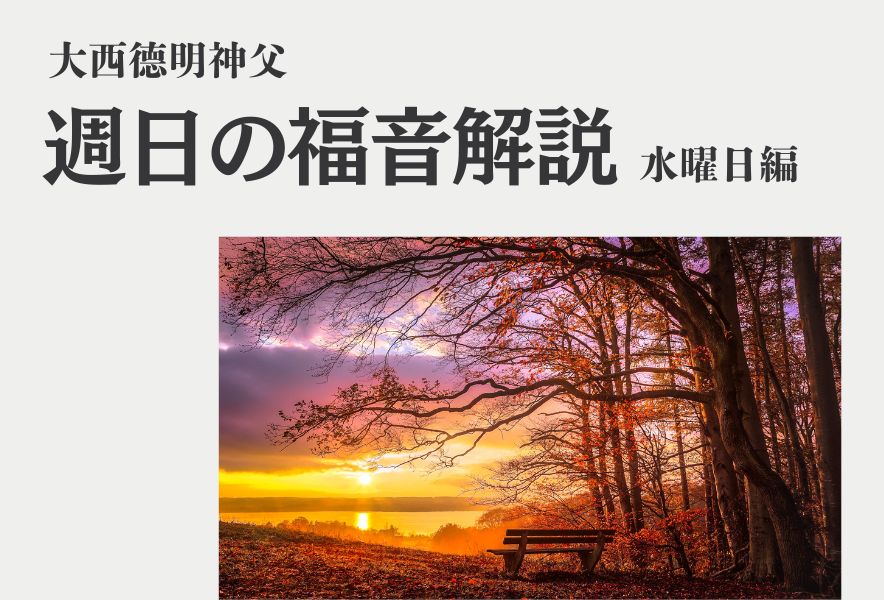ルカによる福音書14章25–33節
25 さて、大勢の群衆がイエスと一緒について来たが、イエスは彼らの方に向いて言われた、 26 「だれでも、わたしのもとに来る者は、自分の父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、更に自分の命までも憎まないなら、わたしの弟子になることはできない。 27 自分の十字架を背負って、わたしの後に従わない者は、わたしの弟子になることはできない。 28 あなた方のうち、塔を建てようとするとき、まず腰を据え、完成できるかどうか、必要な費用を計算しない者がいるだろうか。 29 そうしないと、土台を築いただけで完成できず、見ていた人々がみな、 30 『あの人は建て始めたが、完成できなかった』と言って、あざ笑うことになるだろう。 31 また、ある王が、ほかの王と戦おうとして出かけるとき、まず腰を据え、一万人で二万人を率いて来る敵を迎え撃てるかどうか、考えないだろうか。 32 もしできないと分かれば、敵がまだ遠くにいる間に使節を送って、和を請うだろう。 33 だから、同じように、自分の持ち物を一切捨てない者は、だれもわたしの弟子になることはできない」。
分析
ルカによる福音書14章25–33節は、「弟子になるとは何か」という問いに対して、イエスが非常に厳しい条件を提示している場面です。大勢の群衆がイエスの後に従っている中で、イエスはあえてこのような強い言葉を語ります。「父母妻子兄弟姉妹、自分の命までも憎まなければ弟子になれない」「自分の十字架を背負わなければならない」「持ち物を一切捨てなければ弟子になれない」──いずれも過激とも思える要求です。
しかし、これは意図的に誇張された命令ではありません。イエスが目指していたのは、単なる人気や一時的な共感を集めることではなく、神の国のために自己放棄できる真の弟子を形成することです。イエスの語る「憎む」という語は、ヘブライ的表現では比較級的意味合い(「それ以下に愛する」「優先しない」)を持ちます。すなわち、神の国とイエスへの忠誠が、いかなる血縁関係や自己保存本能よりも優先されねばならないということです。
譬えとして語られる「塔を建てる者」と「戦争に臨む王」の例は、共に「事前の計算」「費用の把握」を求めるものです。弟子となることは安易な選択ではなく、生涯のリソースすべてを再配置する決断を要します。途中で放棄するならば、土台だけが残り、周囲の笑い者になるとさえ警告されています。
最も核心的な結論は33節にあります。「自分の持ち物を一切捨てない者は、わたしの弟子になれない」。この「持ち物」という語は、単なる物質的財産だけでなく、地位、能力、誇り、計画、人生そのものをも含意しています。つまり、弟子となることは、全的な再出発、再所有、再構成を意味するのです。
この段落の文脈には、イエスがエルサレムへの最終的な旅に向かう途上であるという背景があります。彼はこれから十字架へ向かう。その道に続くということは、避けがたく自己放棄と苦難を引き受ける覚悟を必要とするのです。
神学的ポイント
・信仰は関係の再優先を要求する
イエスは、「父母、兄弟姉妹、自分の命までも憎まねば弟子にはなれない」と語ります。これは関係性の断絶を意味するのではなく、キリストとの関係が、すべてに優先されるべきであるという神の国の優位性を示します。信仰とは、最も深い絆さえも再編成する行為なのです。
・弟子制は自己放棄を伴う歩みである
「自分の十字架を背負ってついて来なければならない」とは、自己実現ではなく、自己放棄による神の意志への従順を意味します。弟子とは、自分の思いや願いを絶対視せず、日々の犠牲をもって神の道を歩む者のことです。十字架は象徴ではなく現実の生き方を表しています。
・信仰は感情ではなく計算された決断である
「塔を建てる者」「戦に行く王」の譬えが示すように、信仰には代償が伴うことを見極める理性と覚悟が求められます。情熱や感情だけで従うなら、途中で挫折し、信仰そのものを破壊しかねません。信仰は思慮深い人生の再設計であり、衝動的な選択ではないのです。
・持ち物の放棄は神の主権の承認である
「持ち物を一切捨てない者は弟子になれない」と語られるとき、それは財産以上に、自己の権利・支配・独立性を手放すことを意味します。弟子となるとは、神に人生の支配権を委ねること。放棄は損失ではなく、神の支配を選ぶ自由の行使なのです。
・弟子の道は少数者の道である
イエスは群衆ではなく、「わたしについて来たい者」に向かって語りました。弟子となる道は大勢の同意を得るものではなく、個人的かつ決定的な選択です。信仰とは孤立を恐れず、十字架を担って進む道。神の国は、まさにそのような覚悟ある者たちによって現されます。
講話
イエスに従うとはどういうことか。今日の聖書箇所は、それに対して正面から問いを投げかけています。「自分の命までも憎まなければ弟子にはなれない」。これは過激な言葉ですが、イエスは私たちの決断を、表面的な共感ではなく、本質的な自己放棄にまで問い詰めておられるのです。
私たちはしばしば、信仰を「加えるもの」として考えがちです。日常の生活に神の助けが欲しい、安らぎや導きを得たい──もちろんそれも重要です。しかし、イエスが求めているのは、生活の一部としての信仰ではなく、人生全体を再構成する関係性です。それは、「塔を建てる者」「戦争に臨む王」の譬えが示すように、代償を正確に見積もり、計算し、それでも従うという覚悟を必要とします。
イエスは十字架に向かっていました。彼の歩みは、栄光ではなく死へと向かっていたのです。その後をついてくる群衆に、イエスはあえて突きつけます。「あなたがたも、同じ道を歩む覚悟があるか?」と。弟子とは、イエスと同じように、自分の十字架を背負い、犠牲の道を選び取る者です。
33節に至り、イエスはこう言い切ります。「自分の持ち物を一切捨てない者は、わたしの弟子になることはできない」。これは、財産だけでなく、地位や願望、誇り、自分の人生設計のすべてを指します。すなわち、キリストの弟子とは、神にすべての所有権を明け渡す者です。そこには確かに痛みがありますが、そこからしか、本当の自由も、神の国も始まらないのです。
イエスに従うことは、気分でも情熱でもありません。日々の決断と継続です。塔を建てるように、費用を計算し、戦いに出るように、心を決めて進むこと。キリストの道に従う者とは、そのようにして最初に「捨てること」から始める者です。私たちは何を捨て、何を得ようとしているのか。弟子として生きるとは、まさにこの問いに向き合い続ける歩みなのです。