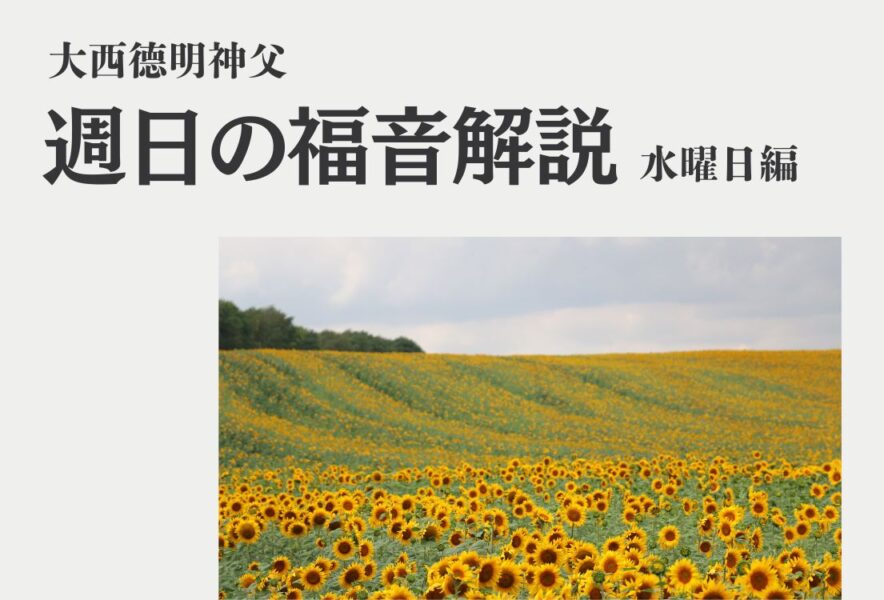マタイによる福音書18章15-20節
15 「もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけの 間で、彼をいさめなさい。もし彼があなたの言うことを 聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことにな る。 16 しかし、もしあなたの言うことを聞き入れなけれ ば、ほかに一人か二人を連れていきなさい。『すべてのこ とは、二人または三人の証言によって確実なものとなる』 とあるからである。 17 もし彼らの言うことも聞き入れなけれ ば、教会に申し出なさい。もし教会の言うことも聞き入 れなければ、彼を異邦人や徴税人と同様にみなしなさい。 18 あなた方によく言っておく。あなた方が地上でつなぐこ とはすべて天でもつながれ、あなた方が地上で解くことは すべて天でも解かれる。 19 さらに、あなた方によく言って おく。どんなことであれ、もしあなた方のうち二人が心を 一つにして地上で願うなら、天におられるわたしの父はそ れをかなえてくださる。 20 二人また、三人がわたしの名に よって集まっている所には、わたしもその中にいる」。
分析
マタイによる福音書18章15-20節は、教会における罪と赦し、対話と共同体の在り方をめぐる極めて実践的でありながら、深い霊的洞察を含む箇所です。ここでは、個人間の罪の問題が、いかに共同体の中で取り扱われ、最終的に神の臨在と一致へと導かれるかが段階的に描かれています。
まず注目すべきは、最初に罪が明らかになったときに、「二人だけの間でいさめなさい」と命じられている点です。これは、問題解決の初手が告発や排除ではなく、個人的な関係回復の試みであるべきだという、非常に繊細かつ高い倫理的スタンスを示しています。ここには、赦しと真実の回復を第一義とするキリスト共同体の性質が滲み出ています。
しかし、それが聞き入れられない場合には、一人か二人を伴って再度接触する段階が指示されます。これは申命記19:15の律法「二人または三人の証言によって物事が確立される」という原則を背景としています。ただしここでも目的は裁きではなく、「確実にすること」、すなわち関係と真実の確認と保証です。
そして、最終段階として「教会に申し出る」ことが命じられています。ここで重要なのは、「教会」(エクレシア)という言葉が福音書においてほとんど使われない中で、ここでは明確に登場することです。これは、マタイの共同体にとって、この言葉がすでに機能的な現実であり、問題解決の場であったことを物語っています。
それでも聞き入れなければ、「異邦人や徴税人のように扱え」と言われますが、ここが非常に逆説的です。なぜなら、イエスはまさに異邦人や徴税人と食事を共にし、愛を示した方だからです。つまり、彼らを排除するというより、再び福音を必要とする対象として接することが暗に示されていると読むことができます。
18節以降では、この関係回復の行為が天の領域にまで届く、すなわち「地上でつなぐことは天でもつながれ、解くことは天でも解かれる」と語られます。これは、赦しと対話において共同体が神の権威を帯びるという、驚くべき約束です。そして続く19節・20節は、一致して祈る者たちの中にキリストが現存するという宣言で締めくくられます。
神学的ポイント
この箇所の神学的焦点は、「キリストの名における関係回復の神聖性」にあります。イエスは罪の問題を単なる道徳の問題ではなく、共同体の霊的健全性の問題として取り扱います。そしてその回復は、一方的な赦しでもなく、権威的な裁きでもなく、丁寧な対話と一致のプロセスの中でなされることが求められています。
特に18節の「つなぐ」「解く」という言葉は、マタイ16:19でペトロに対して語られたものと同じです。そこでは教会の鍵としてペトロ個人に与えられていましたが、ここではすべての弟子たち、すなわち教会共同体全体に与えられています。このことは、教会が赦しを告げる場、神の意思を地上に反映する場として召されているという、深い信頼の表れです。
また、「二人また三人が心を一つにして祈る」ことによって神が働かれるという教えは、数ではなく一致の霊が重要であるという霊的原理を示しています。神は多くの人が集まる大集会に臨在されるのではなく、真実にキリストの名において集まる、少数の者たちの交わりの中にこそおられるのです。
この一致とは、ただの「仲良し」ではなく、対話と葛藤を経てなお繋がり合おうとする努力の中にある一致であり、それはまさに教会の交わりの本質です。
講話
この箇所は、現代の教会にとって非常に具体的かつ痛切な問いを投げかけています。人間関係の亀裂、教会内の摩擦、赦すことの難しさ——これらはどの共同体にも避けられない現実です。しかしイエスは、そのような現実を正面から見据え、「どう向き合うべきか」を語ります。
まず、問題を外に向けず、「二人だけの間でいさめなさい」と言われるイエスの声に耳を傾けたいのです。他人を巻き込む前に、本人と向き合う勇気。それは時に怖く、疲れることです。しかしそれこそが、キリスト的な対話の始まりです。
もしそれでも関係が修復されなければ、証人とともに再び向き合い、それでも難しければ教会が関わる。この段階的なプロセスは、断罪ではなく、希望のためのプロセスです。真実を確かめ、関係を諦めず、神の力に委ねてゆく歩みです。
そして、仮にそれでも関係が修復されない場合、私たちは「異邦人や徴税人のように扱う」ことが求められます。これは切り捨てることではありません。むしろ、イエスが最も近づかれた人々と同じように、再び福音を届けるべき相手として見なすことなのです。赦しの扉は常に開かれているのです。
最後に、キリストの名において二人が集い、祈るなら、神はその真ん中におられるという約束を忘れてはなりません。たとえ私たちが完全でなくても、少数であっても、赦そうとする心、一致を求める祈りの中に、キリストが現にともにいてくださる。これは信仰の中で最も慰め深い真理の一つです。
だからこそ、私たちはつなぐ者でありたいのです。つなぐとは、傷ついた関係の間に立ち、断ち切られた糸をもう一度結び直す行為です。時には沈黙の糸を、時には涙の糸を使いながら、それでもつなぐ者として生きる。そこに、キリストが共におられるのです。