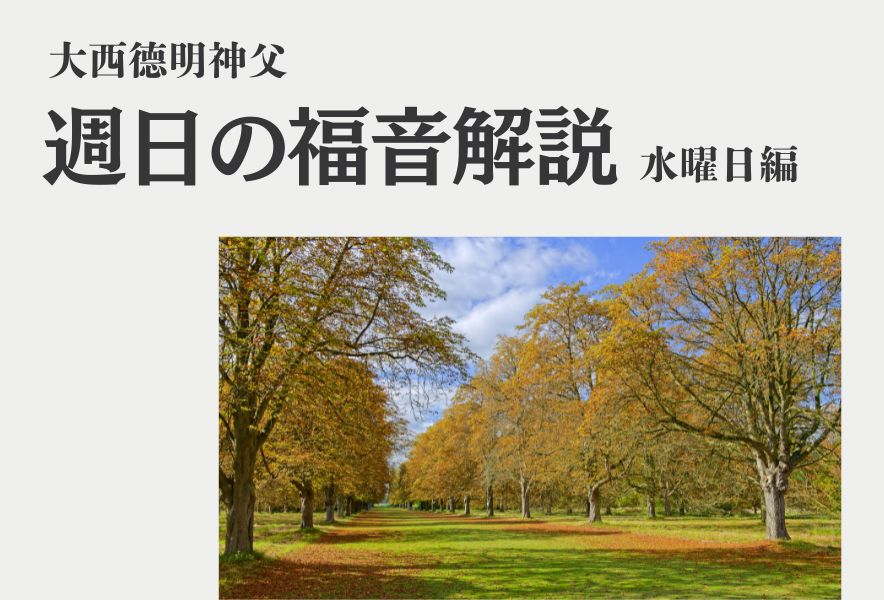ルカによる福音書4章38–44節
38 さて、イエスは会堂を出て、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高熱で苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに願った。 39 そこで、イエスは枕元に立ち、熱をお叱りになった。すると熱は引き、彼女はすぐに起き上がって、一同をもてなした。 40 やがて、日が沈むと、人々はさまざまな病気を抱えている人をみな、イエスのもとに連れてきた。イエスは一人ひとりの上に手を置いて癒やされた。 41 悪霊も、「あなたは神の子です」と叫びながら、多くの人々から出ていった。イエスは悪霊どもを叱りつけ、ものを言うことをお許しにならなかった。イエスがメシアであることを、悪霊どもは知っていたからである。
42 さて、夜が明けると、イエスは人里離れた所に出ていかれた。多くの人々はイエスを捜し回ったすえ、そのもとにやって来ると、自分たちから離れて行かないように引き止めた。 43 しかし、イエスは仰せになった、「わたしはほかの町々にも、神の国の福音を宣べ伝えなければならない。わたしは、そのために遣わされたのである」。 44 そして、イエスはユダヤのあちらこちらの会堂で教えを宣べ伝えられた。
分析
イエスの初期の宣教活動を描く一連の場面です。非常に短い描写の中に、「癒し」「悪霊の追放」「沈黙」「祈り」「移動」といった要素が凝縮されており、イエスのミニストリーの神的主権、人格的関与、そして動的な使命感が明確に示されています。
まず、会堂での出来事(4:31–37)の直後に、舞台はシモン(ペトロ)の家へと移ります。イエスは「会堂から出て」家へ入り、シモンの姑が高熱で苦しんでいると聞くと、彼女の枕元に立ち、熱を叱るという異例の行為をなさいます。ここでの「叱る」という動詞は、通常は悪霊や風、波といった敵対的な力に向けられるものであり、熱もまた「人を支配する敵」として扱われていることが分かります。
イエスの言葉や行為は魔術的でも演技的でもなく、直接的で簡潔、しかも効果的です。熱は即座に退き、癒された彼女はすぐに起き上がり、一同をもてなします。この「もてなした」という表現は、単なる食事の用意以上の意味を持ち、癒しの応答としての奉仕を示唆しています。癒しは終点ではなく、他者への奉仕へと転換される起点なのです。
その後、日没とともに群衆が押し寄せ、多くの病人が連れて来られます(日没後というタイミングは、安息日の制約が解けたことを意味します)。ここで注目すべきは、「一人ひとりの上に手を置いて」癒やしたという点です(4:40)。イエスの癒しは量産型ではなく、常に個別的かつ具体的な関係性の中で行われているのです。
悪霊の追放では、彼らがイエスを「神の子」と叫びますが、イエスはこれを「叱り」、言うことを許されません(4:41)。これは、イエスが自らのメシア性をコントロールし、時と方法を神の計画に従って顕すという「メシアの沈黙」の主題に通じています。悪霊たちの知識は的確でも、その証言は神の栄光を損なうものとされ、拒まれるのです。
そして翌朝、イエスは「人里離れた所」に出て行きます。祈りのためであることが並行記事(マルコ1:35)で示されており、力ある働きの後に孤独と祈りに戻るというイエスの霊的リズムがここにあります。人々はイエスを引き止めようとしますが、イエスは「わたしは他の町々にも神の国の福音を宣べ伝えなければならない」と語り、一つの場所に留まることなく、使命に生きる姿を示します。
神学的ポイント
この一連の描写において最も強く打ち出される神学的メッセージは、「神の国は癒しと告知の両輪によって前進する」ということです。イエスはただ病を癒す奇跡的存在ではなく、神の支配(バシレイア)を現実に導入する方として行動しています。癒しも悪霊の追放も、それ自体が目的ではなく、神の国の訪れのしるしであり、言葉と行為の一致の中で福音は現実となっていきます。
さらに、悪霊に言わせないという点に、イエスの受難に至るまでのメシア性の隠蔽と顕現のタイミングが見えます。イエスは「神の子」であることを真理として持ちながら、その真理が正しく受け取られるためには、受難と復活を経る必要があるという深い神学的洞察がここに埋め込まれているのです。
また、祈りのために人里離れた場所へ行くイエスの姿からは、神の国の働きにおいて自己の霊的中心がいかに重要かが示されています。群衆の称賛や要望に流されず、神の御心を聴き続ける姿勢は、権威と自己抑制の緊張関係の中で生きるイエスの姿そのものです。
そして、「私はそのために遣わされた」と明言する言葉には、イエスの自己認識と使命感が凝縮されています。癒しは愛の表れであると同時に、神の国が到来したという宣言的行為なのです。
講話
この物語は、現代を生きる私たちに三つの重要な問いを投げかけます。
第一に、「あなたはイエスに何を願い、どう応えているか?」です。シモンの姑は癒された後、即座に「もてなした」とあります。これは、癒しが「自己回復」で終わらず、「他者への奉仕」へと展開される姿を象徴します。私たちも神から多くを癒され、赦され、支えられてきたのではないでしょうか。その恵みは、誰かを支える力となって流れ出しているでしょうか?
第二に、「あなたは沈黙を受け入れているか?」です。悪霊はイエスを正しく認識しながら、その告白は拒まれました。正しい言葉を持っていても、それが神の御心を反映していなければ、真理にはならない。現代は情報と声に満ちていますが、信仰とは時に沈黙に耐えることであり、イエスの沈黙に学ぶことでもあります。
第三に、「あなたは留まろうとするか、遣わされようとするか?」です。群衆はイエスに留まってほしいと願いました。それは当然です。しかしイエスは「ほかの町々へ行かなければならない」と答えました。福音とは「私たちのためだけのもの」ではなく、常に「まだ知らない人々のもとへ向かうもの」です。教会や信仰生活が安定しているときこそ、私たちは問われます——「ここにとどまるか、出ていくか?」
癒しの主イエスは、個人に手を置きながら、群衆に向かって歩き、祈りによって神と交わりながら、次なる地へと進んでいかれる方です。私たちもまた、その道を共に歩む者として、今日どこへ遣わされ、誰のために手を差し伸べるべきかを、静かに問い直すべき時なのかもしれません。