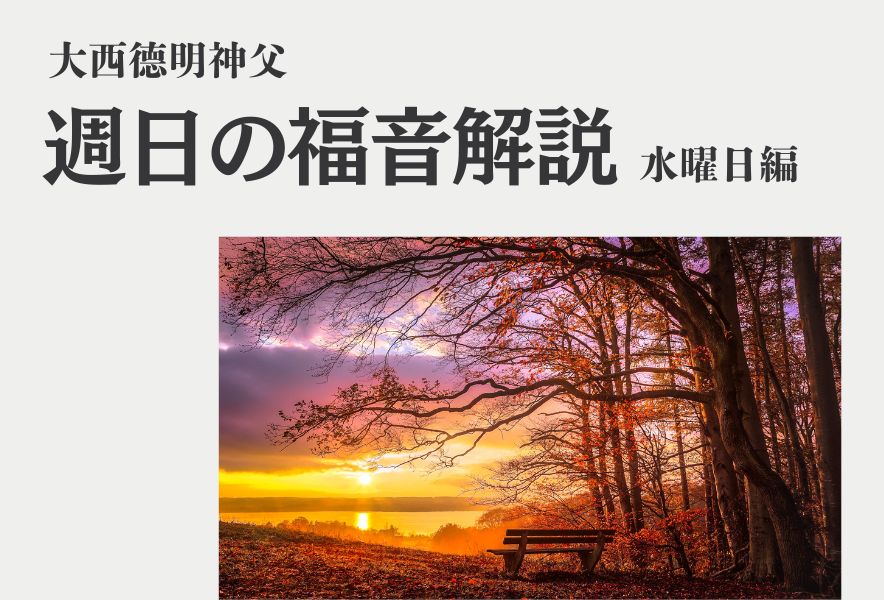ルカによる福音19章11-28節
11 人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスは更に一つのたとえを話された。エルサレムに近づいておられ、人々が、神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。 12 そこで、イエスは言われた、「ある身分の高い人が、王位を受けて帰るために、遠い国へ旅立つことになった。 13 彼は十人の僕を呼び、十ムナを渡して言った、『わたしが帰って来るまで、これで商売しなさい』。 14 しかし、国民は彼を憎んでいたので、後から使節を送り、『この人に王になってほしくない』と言わせた。 15 さて、彼は王位を受けて帰って来ると、金を渡しておいた僕たちが、それぞれどれだけもうけたかを知ろうとして、彼らを呼び寄せた。 16 最初の者が進み出て言った、『御主人様、あなたの一ムナで十ムナもうけました』。 17 主人は言った、『よい僕だ。よくやった。お前はごく小さな事に忠実であったから、十の町を支配する者になれ』。 18 二番目の者が来て言った、『御主人様、あなたの一ムナで五ムナになりました』。 19 主人はこの者にも言った、『お前も五つの町を治めよ』。 20 また、ほかの者が来て言った、『御主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。 21 あなたは、預けなかったものも取り立て、蒔かなかったものも刈り取る、厳しい方なので、恐ろしかったのです』。 22 主人はその者に言った、『悪い僕だ。わたしは、お前のその言葉でお前を裁こう。わたしが預けなかったものも取り立て、蒔かなかったものも刈り取る、厳しい人間だと知っていたのか。 23 では、なぜ、わたしの金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば、わたしは帰って来たときに、利息付きでそれを受け取れたはずだ』。 24 そして、そばに立っていた人々に言った、『その一ムナを彼から取り上げて、十ムナ持っている者に与えなさい』。 25 人々が、『御主人様、あの人はもう十ムナ持っています』と言うと、 26 主人は言った、『言っておくが、持っている者はだれでも与えられ、持っていない者は、持っているものまでも取り上げられる。 27 わたしが王になるのを望まなかったあの敵どもを、ここに連れて来て、わたしの前で打ち殺せ』」。 エルサレム入城 (マタ21・1-9、マコ11・1-10、ヨハ12・12-19) 28 イエスはこのように話してから、先頭に立って、エルサレムへ上って行かれた。
分析
このたとえは、イエスがエルサレムに近づく中、「神の国はすぐにも現れる」と考えていた人々に向けて語られたものです。表面的には「主人と僕」「忠実と怠慢」「報いと裁き」を描いていますが、背景にはメシア王権の性質と到来の時期についての誤解がありました。王が遠国へ旅立つという構図は、古代の実例――例えばヘロデ大王の子アルケラオスがローマで王位承認を受けたこと――を下敷きにしているとも考えられ、聴衆には政治的・宗教的緊張感を想起させたはずです。
ここで語られる王はイエスを象徴し、彼の「出発」は昇天、「帰還」は再臨を表します。この「王が不在の時間」に、弟子たちはそれぞれに与えられたムナ――神の恵み、福音の使命、信仰の働き――をもって忠実に応答するよう命じられます。王は数や成果ではなく、「忠実さ」を評価の基準とします。
一方で、「主人が厳しい方だと思った」としてムナを隠していた僕は、信頼に基づく行動ではなく、恐れによって不作為に陥りました。神の国における裁きは、積極的な反逆者だけでなく、「応答しない者」にも向けられるという厳しさが、このたとえには表れています。
さらに、「持っている者は与えられ、持っていない者は取り上げられる」という逆説的な言葉は、神の国の成長の原理を示し、信仰の世界が停滞を許さないダイナミズムに満ちていることを告げています。
最後に、「王になるのを望まなかった者たちを連れてきて、目の前で殺せ」との厳しい言葉は、神の王権の拒絶がただの意見の相違では済まないことを強調します。この箇所は、恵みと裁き、信仰と責任、王の権威と僕の自由がいかに交錯しているかを問う、終末論的かつ倫理的なたとえです。
神学的ポイント
・中間時期における責任の明確化
王が旅立ち、帰ってくるまでの間は、イエスの昇天から再臨までの時代を象徴しています。この期間に弟子たちは放任されているのではなく、明確な使命を託されています。信仰とは待つことではなく、信託に応じて働くことです。
・忠実さは成果より重要視される
王は「小さな事に忠実だった」と僕を称賛します。これは神が数や大きさではなく、「心の応答と誠実さ」に目を留めることを示しています。ムナが十になったか五になったかよりも、それにどう取り組んだかが問われているのです。
・神の誤認識が信仰を歪める
三番目の僕は「主人は厳しい方」と思い込み、行動を控えました。この歪んだ神理解が信仰の行為を妨げ、不信仰の実を結びました。正しい神認識は、信仰的生活の出発点です。
・神の国は成長の動的原理を持つ
「持っている者はさらに与えられ…」という原理は、信仰が成長志向であることを示します。与えられた恵みを用いることによって、人はさらに成長し、神の計画に参与する者となっていきます。停滞は後退につながります。
・王権拒否への裁きは決定的である
最後に語られる厳しい裁きは、神の支配を拒否することの結果の深刻さを告げています。王権の拒絶は単なる不信ではなく、神の秩序そのものへの反逆であり、そこには最終的な断罪が待っています。
講話
このたとえは、イエスがエルサレムに向かう緊張の中で語られました。人々はメシアが即位し、神の国が即座に現れることを期待していましたが、イエスは「ある王が旅に出る」という構図で、それが即時には起こらないことを語ります。王が不在の間に僕たちに託される責任、それが中心テーマです。
十人の僕は、それぞれに同じ一ムナを与えられます。つまり、すべての人が等しく、神からの使命を受け取っているという前提があります。重要なのは、そこからどう応答するかです。十ムナを生み出した者も、五ムナの者も、「小さなことに忠実だった」と評価され、報いを受けます。イエスの視点は成果主義ではなく、「忠実さ」にあります。神の国においては、外的成果よりも、どのように誠実に召命に応えたかが問われます。
しかし、三人目の僕は「主人が厳しい方だと思った」と言い、ムナを隠してしまいます。これは、神の像が歪んでしまった信仰者の姿を映します。誤った神理解は、信仰の応答を妨げ、最終的には裁きを招くのです。信仰の出発点には、神がどのようなお方であるかという正しい認識が不可欠です。
「持っている者はさらに与えられ…」という言葉は、神の国の逆説的な原則です。信仰を用いる者は、さらに多くの成長と機会を与えられますが、用いない者はすでに与えられたものさえ失います。これは決して不公平ではなく、信仰が静的ではなく、ダイナミックなものであることを示しているのです。
最後に語られる「王を拒んだ者たちへの裁き」は、聞く者に衝撃を与えます。しかし、これは神の国の主権が、あいまいなものではなく、明確な決断を迫る性質をもっていることの証しです。神の支配を受け入れるか、拒むか――それは中間のない問いであり、永遠の命と裁きの分かれ道となります。
私たちは今、王が一時不在の時代を生きています。王が帰還されるその日に備え、与えられた一ムナをどう用いるのか。その応答こそ、信仰の真価が問われる場所なのです。