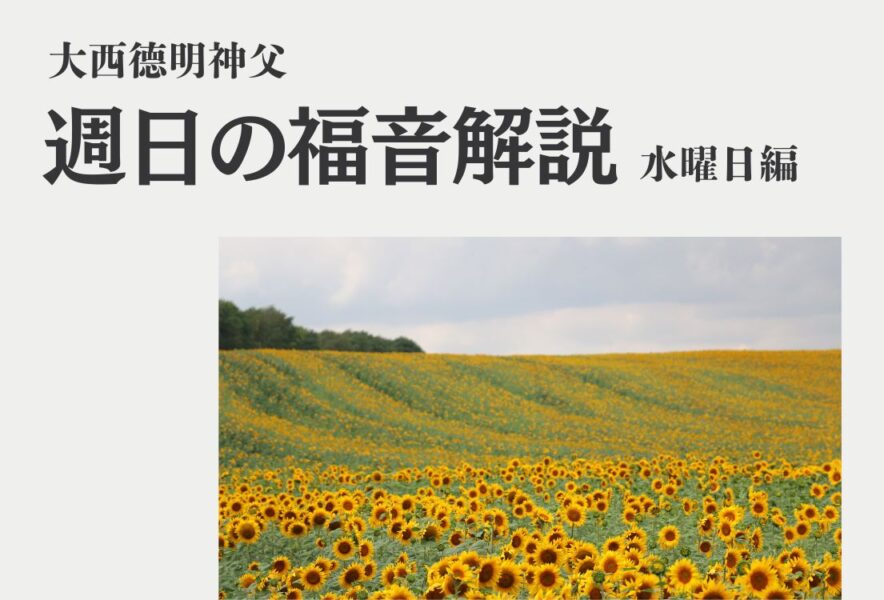マタイによる福音書20章1–16節
1 「天の国は次のことに似ている。ある家の主人がぶどう園で働く者を雇うために、朝早く出かけた。 2 彼は一日一デナリオンの約束で、労働者をぶどう園に送った。 3 九時ごろ、再び市場に出かけると、何もせずに立っている人たちがいたので、 4 彼らに言った、『あなた方もぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払おう』。 5 彼らは出向いて行った。主人はまた十二時ごろと三時ごろにも出かけて、同じようにした。 6 さらに五時ごろ、出かけると、ほかの人たちが立っていたので、『なぜ何もしないで、一日じゅうここに立っているのか』と言うと、 7 彼らは『誰も雇ってくれないからです』と答えた。そこで、主人は彼らに、『あなた方もぶどう園に行きなさい』と言った。 8 夕方になって、ぶどう園の主人は管理人に言った、『労働者たちを呼び、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで、賃金を払いなさい』。 9 そこで、五時ごろに来た者たちが来て、それぞれ一デナリオンずつ受け取った。 10 最初に来た者たちが来て、それよりも多くもらえるだろうと思っていたが、彼らが受け取ったのも一デナリオンであった。 11 それを受け取ると、彼らは主人に不平をもらして言った、 12 『最後に来た者たちは一時間しか働きませんでした。それなのに、一日じゅう労苦と暑さを辛抱したわたしたちと同じように扱われる』。 13 主人はそのうちの一人に答えて言った、『友よ、わたしはあなたに何も不正なことはしていない。あなたはわたしと一デナリオンの約束をしたではないか。 14 あなたの分を取って帰りなさい。わたしはこの最後の人にも、あなたと同じように支払いたいのだ。 15 わたしが自分のものを自分のしたいようにするのが、なぜいけないのか。それとも、わたしの気前のよさを、あなたは妬むのか』。 16 このように、後の者が先になり、先の者が後になる」。
分析
このマタイによる福音書20章1–16節、いわゆる「ぶどう園の労働者のたとえ」は、イエスの語る「天の国」の逆説的性質を極めて鮮やかに描くたとえです。私たちの常識、倫理観、労働観を挑発しつつ、神の国の恵みがいかなる論理によって支配されているかを明らかにします。
物語は、「ある家の主人」が朝早く働き手を探しに出かけるところから始まります。「一日一デナリオン」という契約は、当時の労働者の日給の標準額であり、公正な取り決めです。しかし、その後、主人は三時間おきに(9時、12時、15時)さらには夕方(17時)にも市場に行き、「誰も雇ってくれない人々」を見つけては、労働に招きます。
ここで注目すべきは、「何もしないで立っていた」という描写です。これは単なる怠惰ではなく、労働の機会を得られずに取り残された存在たちであることを示しています。彼らは社会から必要とされていない、無視された人々。ぶどう園の主人はそのような人々を見つけ、労働へ、すなわち「生きる意味と尊厳のある場所」へと招き入れるのです。
そして夕方、賃金の支払いが始まります。驚くべきは、「最後に来た者」から支払いが始まり、しかも彼らも「一デナリオン」を受け取ること。最初に働き始めた者たちは当然「もっともらえるだろう」と期待します。しかし彼らにも、一デナリオンが与えられると、不満を抱きます。
この不満は一見、正当です。「もっと長く、もっと苦労したのに、なぜ同じなのか」と。しかし、ここで主人は言います。「わたしはあなたに不正をしていない」「約束通り払った」と。そして核心的な問いを投げかけます——「わたしの気前のよさを、あなたは妬むのか?」
神学的ポイント
このたとえの最も深い神学的メッセージは、「神の国は報酬の公平さではなく、恵みの気前よさによって支配されている」という点です。人間の視点では、努力した分だけ報いが与えられる「功績主義」が常識です。しかし神の国では、恵みは働きに応じて配分されるのではなく、神の自由と慈しみによって与えられるのです。
このことは、たとえに出てくる「最後の人」に象徴されます。彼らは働きが短かったかもしれない、だがそれは本人の責任ではなく、機会が与えられなかっただけ。神のまなざしは、「どれだけ働いたか」ではなく、「その人が呼ばれたこと自体」を喜びとして捉えるのです。
また、最初の労働者たちが受け取ったものに対して不満を持ったことは、人間の中にある比較と優越の欲求を鋭く突きます。イエスの時代、ユダヤ人たちは自分たちこそ神の民として選ばれているという自負がありました。しかし、イエスはここで、後から来た異邦人や罪人たちが「同じ恵みを受ける」ことに対するユダヤ人の妬みやつまずきを見据えて、この譬えを語っているのです。
最後の一節、「後の者が先になり、先の者が後になる」は、このたとえ全体をまとめる逆説的真理の宣言です。神の国では、序列は覆され、恵みによって価値が再定義されるのです。
講話
このたとえは、私たちにとって極めて不都合な福音かもしれません。努力してきた自分、信仰に生きてきた自分、ずっと教会に仕えてきた自分——そんな自分の「当然の報酬」が、後から加わった者と同じであることに、不満を感じてしまう。それは、私たちがどれほど「自分の正しさ」に依存して生きているかを、突きつけるのです。
けれど、このたとえの本質は、私たちがどう評価されるかではなく、神がどのように与えてくださるかにあります。神は、自らのものを自らの自由で分け与える主です。そして、その気前のよさは、私たちが「より多くもらえなかったこと」を嘆くのではなく、「もらえるはずのなかった者にも等しく与えられたこと」を喜ぶためのものです。
あなたは、どの時間に招かれた者ですか?
朝の六時かもしれません。夕方の五時かもしれません。
けれど、誰であれ「ぶどう園に招かれた」——それ自体が、すでに恵みの極みです。
私たちはこのたとえを、自分の「損得」の観点で読むのではなく、神の喜びと慈しみのまなざしに立って読むべきです。なぜなら、そこに初めて「他者の祝福を喜べる心」が生まれ、妬みではなく感謝が生まれ、序列ではなく兄弟としての一致が育まれていくからです。
神の国では、皆が最後の者です。だからこそ、皆が先となる可能性を与えられている。
このぶどう園は、等しく働き、等しく喜び、等しく恵まれる場所なのです。